ミニチュアカー ミュージアム
MAKER メーカー別リスト
Sorry Japanese Only
ミニチュアカー ミュージアム
MAKER メーカー別リスト
RIO (リオ) [1] [2] [3] [4]
概要 |
||
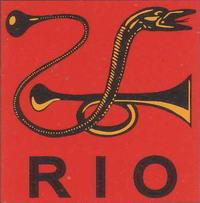 イタリアの老舗ミニカーメーカーRIO(リオ)社の歴史は1961年に発表された1/43サイズのクラシックカー(イターラ 1906)から始まります。このミニカーは大人のコレクターを対象とした非常に精密なもので 、当時の玩具としてのミニカーとは一線を画す画期的なものでした。その後も年に数点づつ同じように精密なクラシックカーが追加されていきました。1986年にはクラシックカーの範疇ではないフェラーリ365GTB デイトナを発表しその後は60年代以降の車も手がけるようになりました。(察するにクラシックカーだけでは商売が成り立たなくなったからでしょう)
2004年に「BEST MODEL」や「ART MODEL」ブランドで1/43サイズのスポーツカーを製作しているイタリアのM4社製にリオのブランドと金型が売却されM4社ブランドとなって現在もメイド イン イタリアで生産を続けています。最近の新製品としてはリオ社時代のモデルをリファインしたモデルなどが発表されています。 |
||
リオのミニカーは亜鉛ダイキャストのボディとプラスチック部品をハンドメイドで組み立ててあり発表された当時最も精巧なミニカーでした。(お値段はダイヤペットの国産ミニカーが450円ぐらいの時に1200円~1500円でした) クラシックカーにはつきもののランプ、レバー、ホーンなどの細かい部品だけではなく、ボディ下回りのフレーム構造やエンジン部分も忠実に再現されています。カラーリングもカラフルで美しい仕上がりで、ドア開閉などのちょっとしたギミックが付いているものもあります。特に初期に作られた1900年代のフィアット車などは現在の精密なミニカーにもひけを取らない素晴らしい出来映えで、あまりモデル化されていないベテラン期のミニカーとしても貴重なものです。
M4社のブランドとなる以前のリオ社のミニカーは一部の限定生産品を除いて絶版となったものがなく、過去に発表された全モデルがカタログに掲載されていました。もちろん全モデルがコンスタントに生産されていた訳ではなく単発的なロット生産がされていたのだと思いますが、実際に何十年も同じモデルが作られていたようです。なおM4社のブランドとなってからはほとんどのモデルが絶版扱いとなったようです。
リオのミニカーは大別すると4つのシリーズに分けられます。まず型番1から始まる基本シリーズ(SERIE NORMALE)、型番R1から始まるレーシングカーシリーズ(SERIE RACING)、型番A1から始まるクラシックトラックシリーズ(SERIE AUTOCARRI)、型番SL001から始まる限定品シリーズ(SERIE LIMITATA)です。以下各シリーズ別に分類して画像で紹介します。(なお数が多いので何回かに分けての紹介となります) |
||
RIOの箱 |
||
| リオは歴史が長いので箱の種類もたくさんあります。代表的な箱は以下のようになっています。 | ||
 60年代の初期型番に使用された箱 (中箱はありません)  80年代まで使われていた箱 大小の2サイズがあり箱の色は型番別 に全て異なります  左の箱の中の透明プラスチックの 中箱 4カ国語で書かれた解説書も入っています |
||
 90年代以降に使われた箱 以前の箱より一回り大きい2サイズで 製品ラベルを貼って共通化してます  小さいサイズの箱には製品ラベル のない専用の箱もあります  最近のジオラマ仕立ての箱 |
||
RIO 基本シリーズ(SERIE NORMALE) 一覧 ページ1 一部の画像はマウスカーソルを乗せると画像が変わります |
||
No.1
 ITALA TARGA FLORIO 1906 ITALA TARGA FLORIO 1906イタラー タルガフロリオ リオの最初のミニカー No.2
 ITALA PEKING-PARIS 1907 ITALA PEKING-PARIS 1907イタラー 北京-パリ No1の北京-パリレース仕様 |
||
No.4
 FIAT 501 TORPEDO 1919 FIAT 501 TORPEDO 1919フィアット 501 トルペード No3の幌を上げたタイプ 緑色ボディ(初期モデル?)の色違いが有ります No.5
 ALFA ROMEO P3 1932 ALFA ROMEO P3 1932アルファ ロメオ P3 アルファのレーシングカー |
||
No.7
 FIAT 0 SPIDER 1912 フィアット 0 スパイダー No6のスパイダー No.9  ISOTTA-FRASCHINI 8a 1924 イソッタ フラスキーニ 8a No8のドライバー席の屋根が無いタイプ |
||
No.10
 BIANCHI LANDAULET 1909 ビアンキ ランドレー 屋根の飾りはルーフラック No.11
 BIANCHI LANDAULET 1909 ビアンキ ランドレー No10の幌を下げたタイプ |
||
No.13
 FIAT 508 BALILLA 1932 FIAT 508 BALILLA 1932フィアット 508 バリッラ 青色ボディの色違いが有ります No.13/P
 FIAT 508 BALILLA 1932 FIAT 508 BALILLA 1932LANCIO PUBBLICITARIO フィアット 508 バリッラ 広告板 名前(バリッラ)の由来となったポスターのついた ジオラマバージョン(1997年頃に追加) No.14  FIAT 2 1910 FIAT 2 1910フィアット 2 |
||
No.15
 ISOTTA-FRASCHINI 8a SPIDER 1924 ISOTTA-FRASCHINI 8a SPIDER 1924イソッタ フラスキーニ 8a スパイダー No8のスパイダー No.16
 CHALMERS-DETROIT 1909 CHALMERS-DETROIT 1909チャルマーズ デトロイト リオ初のアメリカ車 No.17  MERCEDES TOURISTE 1909 MERCEDES TOURISTE 1909メルセデス ツーリスト リオ初のドイツ車 |
||
No.18
 BIANCHI 15/20CV 1906 BIANCHI 15/20CV 1906ビアンキ 15/20CV 客室が板バネで吊られています No.20  FIAT 18BL AUTOBUS 1915 FIAT 18BL AUTOBUS 1915フィアット 18BL バス フィアットの乗り合いバス |
||
No.21
 MERCEDES-BENZ 770K CABRIOLET 1938 MERCEDES-BENZ 770K CABRIOLET 1938メルセデス ベンツ 770K カブリオレ フェンダーが濃い色となっているツートンカラー の色違いがあります No.22
 MERCEDES-BENZ 770K CABRIOLET 1938 MERCEDES-BENZ 770K CABRIOLET 1938メルセデス ベンツ 770K カブリオレ 他社があまりモデル化しないナチス時代のベンツ No.23  FIAT 60CV 1905 FIAT 60CV 1905フィアット 60CV |
||
|
No.25 フィアット 24CV ダブル フェートン |
||
No.27
 FIAT 24CV LIMOUSINE 1905 FIAT 24CV LIMOUSINE 1905フィアット 24CV リムジーン No.28
 BIANCHI 20/30CV LANDAULET 1905 BIANCHI 20/30CV LANDAULET 1905ビアンキ 20/30CV ランドレー 馬車時代そのままの優雅な形の客室 No.29  MERCEDES SIMPLEX 1902 MERCEDES SIMPLEX 1902メルセデス ジンプレックス |
||
No.30
 DE DION-BOUTON VICTORIA 1894 DE DION-BOUTON VICTORIA 1894ド ディオン ブートン ヴィクトリア 蒸気トラクターと客車のセット 座席や床の色合いが微妙に違うものが有ります No.31
 FIAT 8CV 1901 FIAT 8CV 1901フィアット 8CV フィアットの一号車 No.32 |
||
No.33
 MERCEDES LIMOUSINE 1908 MERCEDES LIMOUSINE 1908メルセデス リムジーン 屋根にあるのは旅行用荷物 No.34
 RENAULT X 1907 RENAULT X 1907ルノー X 屋根の飾りはルーフラック No.35
 RENAULT AG FIACRE 1910 RENAULT AG FIACRE 1910ルノー AG フィアクル |
||
No.36
 BUGATTI T41 ROYALE 1931 BUGATTI T41 ROYALE 1931 ブガッティ ロワイアル ブガッティ ロワイアルの3号車 No.37
 BUGATTI T41 ROYALE 1931 BUGATTI T41 ROYALE 1931ブガッティ ロワイアル No36の幌を畳んだタイプ 画像のような色違いがあります No.38
 FIAT 18/24CV 1908 FIAT 18/24CV 1908フィアット 18/24CV |
||
No.39
 ROLLS ROYCE PHANTOM II 1932 ROLLS ROYCE PHANTOM II 1932ロールス ロイス ファントム II 緑青色ボディの色違いが有ります No.40
 ROLLS ROYCE PHANTOM II 1932 ROLLS ROYCE PHANTOM II 1932ロールス ロイス ファントム II 画像のような色違いがあります No.41
 LANCIA DILAMBDA 1929 LANCIA DILAMBDA 1929ランチア ディラムダ |
||
No.42
 LANCIA DILAMBDA TORPEDO 1929 LANCIA DILAMBDA TORPEDO 1929ランチア ディラムダ トルペード No.43
No.44
 FORD LINCOLN CONTINENTAL 1941 FORD LINCOLN CONTINENTAL 1941フォード リンカーン コンチネンタル No43の幌を畳んだタイプ |
||
No.45
 DUESENBERG SJ TORPEDO PHAETON 1934 DUESENBERG SJ TORPEDO PHAETON 1934デューセンバーグ SJ トルペード フェートン No.46
 DUESENBERG SJ TORPEDO PHAETON 1934 DUESENBERG SJ TORPEDO PHAETON 1934デューセンバーグ SJ トルペード フェートン No45の幌を畳んだタイプ No.47
 THOMAS FLYER RALLY THOMAS FLYER RALLY NEWYORK-PARIS 1908 トーマス フライアー ラリー ニューヨーク-パリ ラリー優勝車 |
||
No.48
 BUGATTI T50 1932 BUGATTI T50 1932ブガッティ T50 No.49
 FIAT 520 SUPER FIAT V12 DORSAY DE VILLE 1921 FIAT 520 SUPER FIAT V12 DORSAY DE VILLE 1921フィアット 520 スーパーフィアット V12 (オルセーデ ビル) 画像のような色違いがあります No.50
 FORD LINCOLN SPORT PHAETON 1928 FORD LINCOLN SPORT PHAETON 1928フォード リンカーン スポーツ フェートン |
||
No.51
 FORD LINCOLN SPORT PHAETON 1928 FORD LINCOLN SPORT PHAETON 1928フォード リンカーン スポーツ フェートン No50の幌を畳んだタイプ No.52
 RENAULT 40CV TORPEDO 1923 RENAULT 40CV TORPEDO 1923ルノー 40CV トルペード No.53
 RENAULT 40CV SPORT 1923 RENAULT 40CV SPORT 1923ルノー 40CV スポーツ No52のダブル・カウル・フェートン・タイプ |
||
| No.54以降はRIO2に続きます。 | ||
バリエーションについて |
||
| リオのバリエーションですが上記のように長期間生産されていますので同じ型番とはいえ作られた時期によって違いがあります。初期のモデルではボンネットや幌を固定する革ベルトに実際の皮革が使用されているのですが、70年代になるとこれがプラスチック製に変わっています。(皮革材質ベルトは長期保管中に腐食されやすいので注意が必要です) 同様に初期に作られた物は金属光沢のメッキ部品が古びた感じがするくすんだメッキですが、これも技術の進歩でピカピカの綺麗なものに変わっています。以下の画像がその実例です。ボンネットを固定しているベルトが皮革からプラスチックに変更されています。 | ||
 型番No.2 初期に製作されたもの  型番No.2 70年代に製作されたもの |
||
| またボディカラーが変更されているものもあります。(私が知っている色違いは一覧の画像下にコメントとして記載してあります) なおバリエーションではありませんが、長期間の保存中にプラスチック製ホイールが溶けてしまう問題(これは70年代のミニカーによく起こるもの)があります。途中から材質を変えているようで80年以降に生産された物では発生しないようです。 | ||









