ミニチュアカー ミュージアム
自動車の歴史 時代/自動車メーカー別
Sorry Japanese Only
ミニチュアカー ミュージアム
自動車の歴史 時代/自動車メーカー別
MITSUBISHI TREDIA 1982 JAPAN

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約4.28m 全幅約1.66m エンジン 変速機: 4気筒 1.8L 135HP 5段変速 3段自動変速
性能: 最高速165km/h データーベースで三菱 コルディア/トレディアのミニカー検索
三菱 トレディア 日本 1982年
三菱 トレディアはミラージュ IIをベースにしたセダンで、前述したコルディアと同時に1982年に発表されました。自社のランサー フィオーレと競合する車で、多分フィオーレよりも上級な車という位置づけだったのでしょうが、あまり存在感のない車でした。エンジンはコルディアと同じ4気筒1.8L(135HP)/1.6L/1.6Lターボ(115HP)と1.4Lを搭載し、3段AT/5段MTで最高速165km/h(1.8L)の性能でした。
コルディア同様にマイナーチェンジでパートタイム4輪駆動仕様が追加されるなどしましたが、目立った特徴がなかったこともあって営業的には失敗した車だったようです。1987年に生産中止となりコルディア同様に一代限りの車となりました。
ミニカーは1982年に発売されたダイヤペット製の当時物です。前述したコルディアと同じ11番工場製で、これも元々は実車販促用ノベルティとして作られたものでした。このトレディアはフロントグリルなどはまずまずの出来ばえですが、キャビン部分がやや小さ目な感じがしてプロポーション的にいま一つでした。塗装の下地処理が悪かったのでしょう、経年変化で左前フェンダーなど塗装の一部が荒れています。ボンネット/ドア/トランクが開閉するギミック付きです。実車の人気がなかったことを反映して、コルディアのミニカーはこの当時物しかありません。三菱が販促用ノベルティとして使わなければ、トレディアのミニカーはたぶん作られなかったことでしょう。 以下はフロント/ボンエットを開いたエンジンルームの画像とリア/トランク開閉の画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)


このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります
http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=1046
MITSUBISHI PAJERO 1982 JAPAN

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約4m 全幅約1.68m エンジン 変速機: 4気筒 2.3Lディーゼルターボ 95HP 5段変速
性能: 最高速145km/h パートタイム4WD データーベースで三菱 パジェロのミニカー検索
三菱 パジェロ 日本 1982年
三菱を代表するSUV(スポーツ ユーティリティ ビークル) パジェロが1982年に登場しました。ピックアップトラックのフォルテをベースにした本格派のアウトドア用4輪駆動車で、ジープの居住性を向上させたような車でした。当初は4ナンバーの商用車登録で、ハードトップとキャンバストップの2タイプがありました。エンジンは4気筒2L、2.3Lディーゼル、2.3Lディーゼルターボ(95HP)の3種類、5段変速、駆動方式はパートタイム4WD、最高速145km/h(ターボ)の性能でした。
1983年に乗用車登録の2/5ドアワゴンが追加され、ガソリンターボエンジンも設定されました。1985年にパジェロがパリ-ダカール ラリーで優勝したことがきっかけとなったのかどうか定かではないですが、1980年代の後半にアウトドア用4輪駆動車のブームが起こります。(当時の私にはどこがいいのか理解できませんでしたが) パジェロはそのブームの中心となって大ヒットしました。エンジンのハイパワー化と乗用車的な高級化が行われ、パジェロはSUVというジャンルを一般化させた車となりました。このブームの中でトヨタ ハイラックス サーフ、日産 テラノなどのSUVも生まれました。1991年にパジェロ 2代目にモデルチェンジしました。
ミニカーは1982年に発売されたダイヤペット製の当時物です。ダイヤペットの11番工場(製造委託先)製で、初期の2ドア車をモデル化しています。ヘッドライトが小さめなのがいまひとつですが、それ以外は実車の雰囲気がうまく再現されていて、良く出来ていました。タイヤが少し大きめで車高が高いのはこの車のデフォルメとして悪くないです。同時期のランサーやギャランのミニカーと同様に、これも三菱自動車の実車販促用ノベルティとして使われたようです。ボンネット/ドアが開閉するギミック付きです。タイヤなどを変更したパリ-ダカール ラリー仕様もありました。パジェロ 初代の当時物ミニカーではトミカが初期の2ドア車をモデル化していました。当時物以外では、ドイツのリーツェ(1/87)の2ドア ラリー仕様と5ドア車、国産名車コレクションの2ドア、hpiレーシングのラリー仕様などがあります。 以下はフロント/ボンネットを開いたエンジンルームの画像とリアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)


以下は1987年に発売されたバリエーションのパリ-ダカール ラリー仕様 (1/40 型番T73)の画像です。1985年パリ-ダカール ラリーで優勝したパジェロとほぼ同じようなカラーリングですが、優勝車(#189)をモデル化しているわけではないようです。(実車画像→ 三菱 パジェロ 1985年パリ-ダカール ラリー優勝車) (画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)


以下はアシェット製 国産名車コレクションの三菱 パジェロ (1/43 No.52)の画像でメーカーはノレブです。ノレブらしいそつのない造形で実車がうまく再現されていました。フロントグリルや室内などの細部も良く仕上げてあって、なかなか良い出来ばえでした。ただしヘッドライト周りの枠が少し目立ち過ぎで、ヘッドライトが角形のように見えるのはいただけません。 ノレブは型番800107で「6台セット 三菱 パジェロ パリ-ダカール 優勝車 1985、1992、1997、2001、2003、2007」を発売していましたが、1985年の優勝車はこれを流用したラリー仕様のようです。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)


以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)


このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります
http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=1048
HONDA PRELUDE XZ 1982 JAPAN

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約4.3m 全幅約1.69m エンジン 変速機: CVCC4気筒 1.8L 125HP 5段変速 4段自動変速
性能: 最高速180km/h データーベースでホンダ プレリュードのミニカー検索
ホンダ プレリュード XZ 日本 1982年
1982年にホンダ プレリュード 2代目が登場しました。先代と同じ前輪駆動のノッチバッククーペながら、前輪のダブルウィッシュボーン式サスペンションと当時流行だったリトラクタブルヘッドライトを採用して低いノーズのスタイリッシュなデザインとなりました。日本初の4輪ABSや車速感応式のパワーステアリング、クルーズコンピュータなど先進技術が採用されていました。CVCC 4気筒1.8L(125HP)エンジンを搭載し、4段AT/5段MTで最高速180km/hと高性能でした。
当初はフェンダーミラーが付いていましたが、1983年に国産車のドアミラーが解禁されたのでマイナーチェンジ後の後期型でドアミラーとなりました。1985年にアコード用のDOHC 4気筒2L(160HP)エンジンを搭載する2.0Siが追加されました。低いノーズのかっこいいデザインが好評で、初代以上に大ヒットしました。このデザインは女性にも人気があったのでデートに使われる車という意味で「デートカー」と呼ばれました。1987年にプレリュード 3代目にモデルチェンジしました。
ミニカーは1983年に発売されたダイヤペット製の当時物です。ダイヤペットの協力工場の中ではややあくの強い造形をしていた11番工場製で、少しごつい感じに仕上がっていました。黒いプラスチック製のヘッドライトカバー部分が大き目で、低いノーズのイメージがいまひとつでしたが、それ以外はなかなかの良い出来ばえでした。ボンネット/ドア/トランクが開閉するギミックに加えてサンルーフも開閉します。プレリュード 2代目の当時物ミニカーはこれしかありません。当時物以外ではアオシマのコールドキャスト製、コナミの1/64、トミカ リミッテドの前期型と後期型、ハイストーリー(レジン製)の後期型、MARK43(レジン製)の後期型などがあります。 以下はフロント/ボンネットを開いたエンジンルーム画像とリア/トランク開閉の画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)


このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります
http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=1062
SUZUKI CERVO 1982 JAPAN

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約3.2m 全幅約1.4m エンジン 変速機: 2ストローク 3気筒 539cc 28HP 4段変速
性能: 最高速115km/h データーベースでスズキ セルボ/フロンテ クーペのミニカー検索
スズキ セルボ 日本 1982年
1970年にスズキ フロンテは3代目にモデルチェンジしました。(実車画像→スズキ フロンテ 1970) 先代の曲面を多用したデザインから直線的な2ボックスのデザインとなりました。エンジンは先代と同じ空冷2サイクル3気筒356㏄(31-36HP)で、1971年に水冷エンジンが追加されました。1971年にフロントをベースにした2シーターのスポーツカー フロンテ クーペが登場しました。(実車画像→スズキ フロンテ クーペ 1971)
フロンテ クーペの最大の特徴はそのデザインで、低い車高に低いノーズ、それに合わせた角形ヘッドライト、深く傾斜したフロントウィンドー/ファーストバックのスタイルは軽自動車ながらかっこよくセンスの良いデザインでした。これはイタル デザインのG.ジウジアーロが提案したワンボックス車のプロトタイプをベースにして、スズキのデザイナーがアレンジしたそうです。(実車画像→ ワンボックス プロトタイプ) 外観だけではなく室内もバケット式のシート、6連の丸形メーターが並ぶインパネ、温度計付きのオーバーヘッドコンソールとスポーツカーそのものでした。リアに搭載されたエンジンは2ストローク3気筒356㏄(37HP)で、最高速は130㎞/hを超えたそうで結構早かったようです。1972年に4人乗りの2+2が設定され2+2に人気が集まったので2シーターは廃止されました。1976年に排ガス規制が強化され軽自動車の排気量が550㏄に変更されたので、フロンテ クーペは生産中止となりました。
1977年に軽自動車規格変更に対応したフロンテ クーペの後継車 セルボ 初代が登場しました。ボディはひとまわり大きくなりましたが、基本的なデザインは踏襲されヘッドライトが丸形に変更され、バンパーが大型化されました。室内が広くなったことでりリアシートが大きくなりリアウィンドーがハッチバック化されました。エンジンは539㏄に拡大されましたが、排ガス対策で28HPとパワーダウンしました。先代はコアなスポーツカー志向でしたが、セルボは女性ユーザーをターゲットにしたおしゃれなクーペに路線変更しました。ただ内装は先代同様と中途半端で、当時の軽自動車の売れ筋はスズキ アルトに代表される軽ボンネットバンだったので、セルボはあまり売れませんでした。1982年にセルボ 2代目にモデルチェンジしました。(実車画像→スズキ セルボ 1982年)
ミニカーは2010年に発売されたアシェット製 国産名車コレクションで、メーカーはノレブです。セルボ 初代の最終型の1982年式をモデル化しています。個人的にはセルボではなくフロンテ クーペをモデル化してほしかったのですが、このセルボでも実車のかっこいいデザインがうまく再現されていました。またリアのスリットに墨入れ処理(タンポ印刷)がされているなど細部も丁寧な仕上げがされていて安価な雑誌付きミニカーとしては非常に良い出来ばえでした。これ以外のセルボ 初代のミニカーは国産名車コレクション 1/24とハイストーリー(レジン製)があります。フロンテ クーペのミニカーはダイヤペットの1/30、京商のポリストーン製 1/43、コナミの1/64、ハイストーリー(レジン製)があります。 以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)


このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります
http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=1469
GM CHEVROLET CAMARO Z28 1983 USA

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約4.88m 全幅約1.85m エンジン 変速機: V型8気筒 5L 150HP 5段変速/4段自動変速
性能: 最高速200km/h データーベースでシボレー カマロ 3代目以降のミニカー検索
GM シボレー カマロ Z28 アメリカ 1983年
1982年にGM シボレー カマロ 3代目が登場しました。シャーシが一新されてボディが少し小さくなりました。同時期に登場したポンティアック ファイアーバード 3代目と同じシャーシを使う兄弟車でした。基本的なスタイルは2代目を踏襲していましたが、カマロとしては初のハッチバックを採用したクーペとなりました。奥まって配置された角型4灯式ヘッドライトと大型のリアウィンドが特徴でした。グレードはスポーツクーペ、ベルリネット、高性能版のZ28がありました。当初のエンジンは4気筒2.5L(90HP)、V型6気筒2.8L、高性能版Z28用V型8気筒5L(145-165HP)がありました。
ストックカーレースIROC(International Race of Champions)に因んで名付けられ、1985年に追加された高性能版IROC-Zはエンジンをパワーアップし足回りを強化していました。1986年に4気筒エンジンが廃止されました。1987年にTバールーフではない本物のコンバーチブルが復活し、IROC-ZのオプションとしてV型8気筒5.7L(220HP)エンジンが復活しました。1991年にIROC-Zが廃止され、Z28はハイマウントのテールスポイラーとボンネット上にダミーのエアダクトが追加されました。1993年に4代目にモデルチェンジしました。(実車画像→ GM シボレー カマロ 1993)
ミニカーは1988年に発売されたソリド製です。ヘッドライトにカバーを付けたレース仕様をモデル化しているようです。(市販車にはカバーが付いていません) このミニカーは1984年に型番1338で発売されました。それは廉価版ミニカーでしたので安っぽいフリーホイールが付いていましたが、この型番1509はHIFIシリーズとして再生産されたもので、少しマシなホイールに変更されていました。プロポーションは悪くないのですが、元々廉価版だったので 全体的に簡素な作りで特徴的なヘッドライトが再現されていないのであまりカマロ 3代目らしくないです。ただこの当時の量産ミニカーはこの程度の出来ばえの物がほとんどでした。ドアが開閉するギミック付きですが、室内も簡単な造形でした。ソリドはYESTERDAYシリーズ(型番1815)と別ブランドのべレム(型番V506)でも同じ物を発売していました。これ以外のカマロ 3代目のミニカーはジョニーライトニングの1/64、ホットホイールの1/64、コーギーのストックカー仕様、サンスターのIROC-Z 1/18、デアゴスティーニのアメリカンカー コレクションのIROC-Zなどがあります。 以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)


以下は1984年に発売されたソリド製の当時物 GM シボレー カマロ Z28 (1/43 型番1338)の画像です。上述した最初に発売されたものです。ホイールがフリーホイールになっていることとカラーリングが違うだけで、上述とほとんど同じ物です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)


以下は1987年に発売されたコーギー製の当時物 GM シボレー カマロ Z28 (1/43 型番C108)の画像です。ストックカーレース仕様車をモデル化しているようです。大きく張り出したオーバーフェンダーが付けられ、ストックカーらしいカラーリングになっていました。ただこれは定価600円ほどの廉価版ミニカーでしたので、プロポーションは悪くないですが、仕上げは簡素でした。特に室内でインパネとステアリングホイールが一体成型されているのは興ざめです。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)


以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)
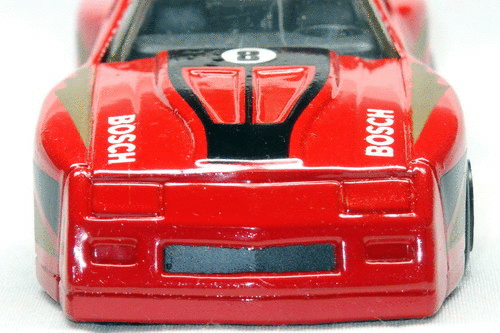

以下は2023年に発売されたデアゴスティーニ製のアメリカンカー コレクションの GM シボレー カマロ IROC-Z (1/43 No.50)の画像です。高性能版IROC-Zをモデル化しています。メーカーは明示されていませんが、イクソです。イクソは2025年に型番CLC562Nで カマロ IROC-Zを発売しましたが、それはこのアメリカンカー コレクションの物とほとんど同じです。カマロ 3代目の出来の良いミニカーが欲しかったので購入しました。プロポーションが良く、実車の雰囲気がうまく再現されていました。特に上記のミニカーでは再現されていなかった特徴的なフロントグリルがうまく再現されていて、期待していた通りの良い出来ばえでした。テールライトなどの灯火類や室内の細部も良く再現されていました。このアメリカンカー コレクション シリーズは安価ながらも、値段以上に良く出来ています。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)



